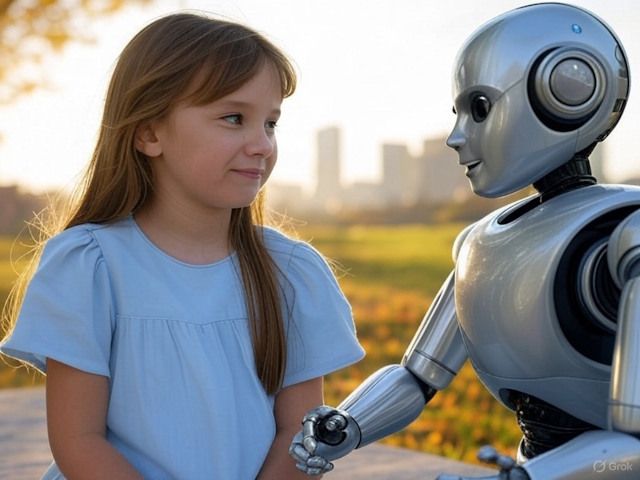
子供の頃、自分で何か書いたものは、手書きで伝えるより他にはない時代だった。印刷をして何枚も同じ物を作ったり、活字にしたりするのには、専門の人などにそういう印刷原稿を作ってもらうよりほかになく、学校の印刷物に自分の書いた文章が掲載されたりすることは、それだけで凄いことでもあった。
小学校の卒業アルバムへの文章は、さすがにガリ版刷りの時代ではなかったが、ボールペン原紙と呼ばれる緑の半透明の用紙にボールペンで強く書いて、それを印刷するような、そんな方法だった。
そのうちに、和文タイプライターから、ワープロ専用機が主流になって、自分も使う機会を得て、そこでキーボードによる文字入力の世界に入り込んだ。キーボードで電子的に文字入力ができて、それがそのまま、用紙に出力されて、もちろん何枚でもそれが印刷できるのであるし、入力した文字はその場限りではなく、フロッピーディスクに保存して何度でも活用できるというのであるから、画期的である。手書きの文化からすると、まるっきり別の世界なのに、結果同じことが出来るのである。
そこからは、自分にとってはその延長上にパソコンがあって、文字入力はワープロソフトからテキストエディタ、そしてブラウザを使ったクラウド上の作業場へと変遷しているわけである。
共通しているのはキーボードによる文字入力である。JISかな入力、ローマ字入力は当初からその通りで、基本的にはそれを覚えた35年も40年も前? と何も変わっていない。その時の同じ入力方法でずっと、和文の文字入力が出来ているのであるから、改めて考えてみると驚きである。もちろん、もっと変わらないのは手書きによる文字書きで、これは文字を覚えて筆記具で文字を書くことを覚えたときから全く何も変わらない。
それはともかく、キーボード入力も随分自分も長い間使っている文字書きの方式になっているので、手書きの筆記と同様に、ある意味懐かしくも、ある意味全く新鮮でもある。
数々のキーボードを使ってきた。ワープロ専用機のキーボードに始まり、それを何機種か経て、パソコンのキーボード、ノートPCのパンタグラフのキーボードから,メカニカル、そして静電容量無接点の機構を備えているRealforcなどへ。
入力方式はローマ字入力から、拡張割り当てを備えた独自のDvorak配列ベースの方式へ、かな漢字変換だけはPC以降はずっとATOKである。
そのような、キーボードによる文字入力との付き合いなので、特別な思い入れ、とまでは言い難いが、それなりの拘りのようなものも出てくるし、長年使っているので、それなり自然に入力もできるようになっている。手書きと違って、確かに文字そのものへの味わいには欠けるのかもしれないが、今時そんなことを言う人も少なくなって、画一的なフォントの文字であってもまた、味わい深いと感じないこともない。
メカニカルな機構のものなど様々使い試した結果、安定して気に入っているキーボードは、やはり東プレのRealforceである。国産で高品質、永く使える。スタンダードなJIS配列だけではなく、より配列が自然なUS配列もあり、HHKBと共に高級キーボードの代名詞みたいになっているが、これが打鍵感も極上で使いやすい。押下圧も45gなり30gなりの軽さが丁度良い。
とにかくRealforce
Realforceのキーボードは、何台も使ってきた。一番古いRealforceはもう15年も前のモデルで、今でも何の問題もなく使える。故障して買い換えたというのではなく、新しいモデルに魅力を感じて、新しいRealforceを導入してきた。
最初のRealforceは、86Uである。テンキーレス、変荷重、US配列のUSB有線モデルで、US配列モデルとしてはRealforceでは初期のほうのモデルらしく、US配列を待望していた人や海外などからよく好まれたモデルではないかと思う。
自分はこれがアイボリーのモデルしかなかったので、黒配色のキーボードが好きな自分はしばらく様子見で手を出さなかったが、HHKBより標準的な配列のモデルが使いたくなって導入したものだった。
その頃、他にFILCOの茶軸キーボードなども使っていて、最初の頃は取り替えてその打鍵感を味わうという程度だったが、しばらくして気付けばRealforceが一番よく使うキーボードになっていた。逆輸入品と思われる、86Uのブラックモデルも買い、その2台でそれぞれのPCで使うようになった。
R2の世代になって、HHKBのPFUとのコラボのモデルを導入した。APC機能がついたりして、プレミアム感のあるRealforceで、等荷重45g、静音スイッチの打鍵感もまた良く、86Uに置き換えて当分の間これが自分の主の環境となったが、また数年かそこらもしないうちに、サブPC用には変荷重の、そして2台目のアイボリーモデル、こちらは変荷重を導入。
そのような変更と並行して、Realforceのテンキー、23U/UBを購入して、これもまたRealforceで、このくらいでだいたい自分のRealforceの好みが定まった。
無線モデルのR3やR2のボディを踏襲したR3Sは、リリースされてからしばらくは様子見としていた。R3はさほど形状が好みでなかったし、R3Sはその後に出たが、これも昇華印刷のモデルが無かったりと、ぴったりと好みに合ったわけではなかったからであるが、それでも幾つかの理由で必要に迫られて、先にR3SのJIS配列、フルキーボードを、その後にR3のUS配列・テンキーレスをと続けて導入した。打鍵感は新品に更新されて、良好である。
そしてついには、30g押下圧のRC1、70%キーボードを導入して、これを使って今に至っている。
これだけ様々使ってきて、正直なところこれが最高と決められないほど、どのモデルも気に入っている。毎日、PC毎に接続した複数のRealforceを打鍵しているが、どれも使う度に快適である。キーボードは本当は何も気にならないほどに使い込めばそれがゴールなのかもしれないが、自分の場合は毎回これが最良の打鍵だと感じるような、これがRealforceなのだと実感できるような感じで、それがRealforceである。
何でも良いからとにかくRealforceのキーボードを使ってみたいという方には、変荷重か45gのモデル。標準的なJIS配列、フルキーボードなどが良い。ひとまずそれで試せば、Realforceの打鍵感と、どのモデルがより好みかはわかってくるのではないかと思うのである。とは言っても、それからまた別のモデルを購入するということには中々、金額的な面を考えても難しいと思うので、そこは賭けという部分は多少ある。
HHKBとRealforce RC1
HHKB Hybrid Type-Sと、Realforce RC1と、よく比較されるこの両方を所有している自分としては、どっちがどうかという点はやはり、押さえておきたいところである。価格帯もだいたい同じで、筐体含めた大きさもほぼ同様ではあるものの、キー数や配列の違いは大きい。RC1は、自分のモデルは30gのものなので、HHKBの45gとの違いもある。
一番違うのはカーソルキーとファンクションキーの有無で、これが60%と70%の差である。HHKBで一番物足りなく思うのは独立したカーソルキーがないことで、これは頻繁にスクロールしたり移動したりする作業を伴う使い方においてはFnキーとの組み合わせでは絶対的に不便である。ただ、文字入力の作業だけで比較するとさほど不便ではない。RC1にはUS配列でもカーソルキーがあるし、加えてファンクションキーも独立しているので、この点での差異は大きい。
また、そのような基本的なところでは、HHKBはBSキーの位置が一つ下段になっているのもかなり大きな違いで、これも入力作業、別のキーボードからの切り替え時に苦労する。
逆に、RC1には右シフトが小さいものしかない。これは70%にカーソルキーを詰め込んだ結果、必然的にそうなるので仕方ない部分ではあるが、意外と右シフトも使っていたようで、小さいと不便なのである。
そのような違いはあって、打鍵感も押下圧が異なるモデルであるからその点が違うということもあるが、それでもHHKBの45gはそれより少し軽い気がして、同じ45gのRealforceのテンキーレス別機よりは軽く打鍵できている。無論30gは明らかにそれより軽いので、打鍵感の快適さはそれぞれ、どちらも良好で、その時の気分で軽すぎると感じたり、45gでも重く感じたりもするのである。
従って、文字入力作業に限って言えば互角。他、様々な作業をするならファンクションキーやカーソルキーを持つRC1のほうが使い易いということである。
押下圧に関しては、好みによるところが大きくどちらも快適であるが、30gはある程度の慣れが必要であるくらいに軽く、それに慣れてしまえば他のものが重く感じてしまうほど快適であることは、使って比較してみてわかったことである。
Realforceを薦めるなら
今まで実際に人にRealforceや他のキーボードを薦めたことはないし、その前に聞かれたこともないが、実際に薦めると想定するなら、どう薦めるのだろうか。
まず、その人がどのくらいのスキルを持っていて、どのようなキーボードを望んでいるかによるのと、あとは予算的にどの程度まで支出できるかということにもよるので、その点を把握するのが第一であろう。
何でも良いからキーボードというのであれば、あえてRealforceなどの良いキーボードではなく、安価な、言われるとおり何でも良いキーボードのうちから、せいぜい標準的な配列を持ったものを薦めるべきである。無線を望むのか有線のタイプを望むのか、あとはテンキーレスかフルキーボードか程度である。このくらいの好みであれば、US配列を選択するという向きは多分ないので、そこは特に触れないでおいてもよい。
標準的な配列を薦めるのは、結局変な配列だと好みが分かれるので、標準的な配列でこれが標準なのだと覚えて、それで使ってもらうほうが後後、今後のキーボード選びに苦労しないようになるからである。従って、この時点で特殊な形状や、キーピッチが確保されていないものなどは除外することになる。
ここまで選べれば、実はキーボード選びの大半は終わってしまうようなものでもあるが、これ以上のスキルを持っているとか、ゲームをするというのであれば、上記に加えて多少機能に拘った製品、ゲーミングキーボードなどから選択をさせても良いのかも知れない。傾向が、変わったキーボードとか、可愛いキーボードなどというのであれば、ちょっと変わった、そういうキーボードから選択させるのも悪くないが、後でサポートが必要な場合は、サポートする側が面倒にならない範囲を想定して選択させるということも重要かもしれない。
さらに上の要求に至る場合、ここでようやくRealforceが選択肢に入ってくる。打鍵感とか、配列がUSであるとか、その辺である。Realforce選びは、まずモデルの選択、テンキーレスかフルか、そしてUS配列かJIS配列かという選択があって、あとは配色、白系か黒系か、刻印の印刷方式もあるが、影響が大きいのは押下圧であるので、ここはしっかりと助言すべきである。
標準的なのはもちろん45gで、基本的にはこれを選ばせておけば問題ないが、今使っているキーボードの状況も勘案して、特に柔らかい打鍵感を望むのであれば、30gという選択をしても間違いではないが、とにかく45gでの打鍵において重く感じるか否かという点がまず基準になってくるので、特別望まない限りは45gモデルで良いのではないかと思う。
30gは特に軽い打鍵感なので、今まで強く打鍵していた人などには少しの慣れが必要であるから、最初は気に入らないかもしれない。ただ、それに慣れてしまうとこれはこれで快適になるので、全く視野に入れないほうが良いというわけでもない。
AOURとキーマップ
AOURは、キーマップの変更無しに、すなわちQWERTY配列のキーボード上で、ローマ字入力のカスタマイズによりDvorak風の和文入力を実現している。わからない人に何のことだかさっぱりかもしれないが、キーの入替をせずに、ただIMEのローマ字定義の変更だけで、全く違った入力方法を実現しているというくらいの意味である。
RealforceやHHKB、あるいはその他のキーボードでも盤面の変更、キーマップの変更に標準的に、ハード的に対応しているキーボードもある。かつて、Dvorak配列やそれをベースとしたACTなどの入力方式では、このようなキーマップ変更が必須で、かつてはどのように実現していたのか知らないが、少なくとも普通の人が普通にできる方法というのではなかったので、自分もAOURは上記のような方法で実装することにした。
ところが最近のRealforce等のキーボードはそういう機能にも対応してきて、ではキーマップの変更と組み合わせた拡張入力というのはできないのかと考えてみた。
だが結論としては、デメリットばかりでメリットがないということが見えてきた。
キーマップを変更すると、ベースの配列が変わる。Dvorakなり、それと類するAOURのベースなりになるわけだが、こうなるとQWERTYの配列とは全く異なった配列になるので、アルファベット、英単語入力が大変なことになるし、QWERTYを基準として設定されているショートカットキーが全く使い物にならなくなる。
それでも、和文入力の時以外はキーマップをデフォルトのQWERTYに戻す切り替えをするか、和文入力専用のキーマップだと割り切って運用することは可能かもしれないと思った。
また、キーマップを変更してそれをベースにするなら、拡張入力以外の定義は標準のままなので、拡張入力に余裕が出来るのかとも思ったものの、標準の定義も定義数には含んでいるから、定義数の余裕は生まれない。
キーマップ変更は特定のキーボード環境でしか使えないので、汎用性も一層低くなる。
そのようなことを考えると、キーマップ変更によるAOURは再定義も必要になって、手間もかかる上に、上記のとおり、メリットがほとんどない。
現行、QWERTY上のベースで設定が出来ているのであるから、そのほかに設定をする、キーマップを変更するような必要はないのである。
コンパクトなキーボード
自分が初めて触ったキーボードはワープロ専用機のキーボードだったが、これはラップトップ型のキーボードだったので、言わばノートPCのキーボードのようなもので、フルキーボードの類とは少し異なっていた。その後に、テンキーのついたデスクトップワープロのフルキーボードを使って、ラップトップのより使い易いと感じた。
PCも最初はPC-98のフルキーボードで、その後はノートPCのキーボードを使うようになってそれから様々なキーボードを触るようになったが、同じ機能がコンパクトなサイズに全て機能として納められているというのは、理想的・魅力的ではあって、当初からそういうコンパクトなキーボードにたいしてもある程度の理解は持っていた。
ファンクションキーやカーソルキーまで省略してしまった配列のHHKBは、初めて見たときはこれで本当に全部の作業に支障が無いのだろうかと不安だったが、ユーザも多く、これは良いというので、自分もそれを使うようになった。
ただやはり、コンパクトすぎて使いにくい部分はあり、フルキーボードは大きすぎるので一般的なテンキーレスを求めて、結局Realforceを使うようになった。
その、コンパクトすぎる60%のHHKBと、丁度良いテンキーレスの間として、70%のRealforce RC1はまさに、もう一つの理想とするところであるというのも、RC1をすぐ選んだ理由の一つである。矢印キーも、ファンクションキーもあるので、テンキーレスクラスと同様に使えるコンパクトということで、これは一番使い易いキーボードになるのではないかと思ったのである。
実際使い始めてみると、右下の矢印キーや小さい右Shiftキーなど気になる部分もあって、完全にこれが一番かというとやはり一般的なテンキーレスのほうが良い面も多いのであるが、60%に比較すると十分に普通に、普通の作業をすることにおいても役立っている。
コンパクトなキーボードとしての到達点はおそらく70%くらいが最低で、75%でも良い。でもコンパクトとして許容最大は80%のテンキーレスという感じである。
フルキーボードは、大きすぎる感じがあるので、多分今後も積極的には選ばず、独立したテンキーを用意して、コンパクトやテンキーレスの左側に配置するという、既に実行している使い方を今後も続けていくつもりである。
RC1で5ヶ月
Realforce RC1を使い始めて5ヶ月経った。当初は、このサイズ感ということでHHKBとの混同があって、BSキーの位置をミスタイプして「\」を打鍵したりしていたが、それはすぐに慣れて、また初めての全30g押下圧ということでも少しの苦戦もあったが、それも問題なくすぐに快適に転じた。
ただ、カーソルキーは良いとして、右のShiftキーが小さいのが意外にもやや難があって、それでも全体的に絶対的に困るというようなことはなく、快適に使えている。高速にというか、他のRealforceと同様に打鍵はできるようになって、基本的にこのキーボードだけでも何にも困らない。ただし、テンキーはあったほうが良いので、左側配置で23Uのテンキーを併用している。
しかし結局は慣れであるので、これを毎日一定時間使っているとこの配列にも慣れて、十分これが良いキーボードになっていくのである。
押下圧30gも、最初は十分に使えるのか不安が大きかったが、使い込んでみると、もう今後は30g一択で良いかなとも思う。ただし、別のRealforceで45gを使うと、しっかり打鍵できる感じはまた格別で、結局どっちが最良かは決められないでいる。
中々、ちゃんとした文章をこれで書く機会がないものの、それでもこのような駄文的なものは書くので、これで十分に役には立っている。重要な筆記具の一つとなっている。
NumLockのLED
NumLockは、数字入力に固定するモードで、そのモードになっている時はキーボードのLEDが点灯して、テンキーから数字入力ができることになっている。フルキーボードの場合は、そのキーボードにあるテンキーの制御状態を示すのでわかりやすいが、テンキーレスキーボードの場合は、テンキーがないので、そのNumLockの表示は何なのかよくからない。
Realfroce R2の場合は、US配列ではノートPCのようなメインキーを代用したテンキー機能もあったので、それを制御するものと思うこともできた。
しかしRealforce R3テンキーレスにはUS配列でもその機能はない。気付けばずっとNumLockのLEDが点灯している。このLEDはバッテリー残量の表示だろうかとも思ったが、どうもそうでもないらしく、常時点灯しているようだ。
外付けで23Uのテンキーを使っているが、このテンキーにはまた個別にNumLockがあるので、つまりR3のNumLock表示はあまり意味が無い。点灯していなくても問題ないのではないか。色々思い出せば、これまで使ってきたテンキーレスも、NumLockキーだけは点灯していただろうか。
R3テンキーレスにはNumLockキーがないので、この点灯をオフにする方法がわからなかったが、方法を調べるとWindowsのオンスクリーンキーボードを表示させ、オプションでテンキーを使う設定にして、そのスクリーンキーボードに表示されるNumLockキーをオフにすることで、R3のLEDも消灯する。
消灯しても、そもそもテンキーレスなのでテンキーが無いため、特に問題はなく、23UもこれでNumLockをオンにしておけば問題ない。ただ、テンキー側で入力すると、R3のLEDも反応して点灯するのが少し気になるところではあるが。
和文入力でもUS配列を
かな入力をする人は、US配列はキーが不十分で困難な面があるが、ローマ字入力を使う一般的な人の場合は、JIS配列ではなくUS配列でも、US配列の方がむしろ快適に和文入力ができると思える。
簡単に言えば、EnterキーやBSキーがホームポジションに近くて打鍵しやすいし、記号キーの配置も合理的で覚えやすい。返還キーとして使うスペースキーも大きくて使いやすいというのが主な理由である。
よく言われるIMEのオンオフ切り替えは、どうしてもコンビネーション操作になってしまうが、Ctrl+Spaceとかに割り当てて、CtrlはAの横にすると、ホームポジションのままでトグル操作ができるので、標準のキーより便利だと思って、自分はJIS配列の時でさえこの操作でオンオフするように設定している。
それが難関だと思う人は少なくないようだが、そのように使い慣れてしまえばむしろこのほうが快適で、自分はずっとそれでUS配列のキーボードを使って、普通に和文入力をしている。US配列に起因して問題が生じたことは一度もない。
むしろJIS配列より快適に感じるので、普通に和文入力をする場合においても、JISではなくUSを選んで良いのではないかと思っている。
Meryエディタ
テキストエディタは、基本的にWZ Editorを使っている。PCを使い始めた、ほぼ当初からずっとWZで、一時期は秀丸も主で使って、でも会社の仕事ではサクラエディタを使って、というテキストエディタの人である。
今も以前も、多くの人はテキストエディタと言ったらやはりコーディングのツールとしてのイメージがあって、そういう用途を第一に考えられたアプリケーションが多い。文章書き作業用途にも十分に活用できるテキストエディタは、それに比べると選択肢は多くない。
特に、縦書きができるエディタは少ない。
WZも秀丸も、これら老舗エディタはもちろん文章書き作業にも多く使われるので、縦書きには対応しているが、フリーのテキストエディタでは、中々そういうものに遭遇しない。サクラエディタも縦書きは出来ない。
少し前から着目していたMeryは、縦書きにも対応していて、これらの高機能なエディタと比較すると機能はそこまで詳細ではないものの、十分に多機能・高機能と言えるアプリケーションになっている。禁則処理や正規表現、GREPはもちろん、アウトラインモードも備え、普通に文章書きをする目的には十分に活用できるものに仕上がってきている。Windows OSとの相性というか親和性が良く、Windows 11のマイカデザインに対応していたり、テーマも豊富で見た目でも心地よくカスタマイズできる。
Emmetが使えるマクロもあったので、HTML作成に関してもほぼこれで問題ない。
WZ等を主で使っている状況であえてこれに全て移行するということはないが、たまに気分を変えて違ったエディタの環境で作業をするという時などはこれが良いし、文章書きに適したエディタとして他人に紹介もし易い。
テキストファイルは汎用性が高いので、どんなアプリケーションでも編集ができる。テキストエディタはもちろん、一太郎やその他のワープロソフトでも可能で、つまりアプリケーションの選択の余地は多い。機能やデザインなど、好みの環境となるものを選べば良い。
WZはおそらく、市販ソフトということもあってライターなどプロの人も結構使っているイメージがある。秀丸は本当の老舗アプリなので、そういう人たちも含めてもっと幅広く使われているイメージがあるが、これらのアプリケーションは、今の若い人たちからすると、多分レガシーなアプリケーションということになるのだろうか。
新配列とAOUR
今さらながら、新配列という言葉を知った。従来のローマ字入力やJISかな入力以外を概ね新配列というのが一般的なようで、AOURも一応新配列の類に入れてもらえるのではないかと思う。
新配列は、種類としては非常に数が多く、有名なもの無名なものたくさんあって、全容の把握は困難であるけれど、意外にAOURのように、ATOKでそのまま実装できる、すなわちローマ字定義のカスタマイズ程度で実装できるというのは少ないかもしれない。
AOURの実装をこの方式にしたのは、AZIKがそうだったことに由来して、この方式で実装するのが自分にとっては一番簡単だったからで、この方式が一番安定性が高いという気がしたからである。DvorakJなどの常駐させるアプリケーションは、あまりその存在を知らなかったし、それで簡単に実装できるとも思っていなかった面があって、これでも実装できるようにしたのはだいぶ後になってからである。
AOURは、定義して使い始めてから現時点で15年以上、きちんと計算すると17年くらいが経つ。そんなに前だったかと思うところもあるが、それだけ使い続けてきたので、もう自分の中ではすっかり当たり前の入力方式になってしまっている。ローマ字入力は、AOURが使えない環境では使うことがあるので、全く忘れてしまったわけではないが、今となってはローマ字入力は初心者か一般ユーザのレベル程度にしか入力できないので自分にとっては効率が悪いのである。
すっかり一つの入力方式が使えるようになっている状態で、新配列へ移行することは学習効率の面でも作業効率の面でもかなり不利である。完全に習得するまでは、それなりに時間もかかるし、その間の入力速度の低下により作業が滞る可能性もある。
AOUR+ATOKの場合、あるいはGoogle日本語入力を併用する場合、IMEの切替程度で元の入力方式に戻せる。新配列はゆっくり練習しつつ、急ぎで入力をしなければならないような場面においては従来方式を使い、新配列がある程度実用的に使えると判断したら、それに移行するような、そういうペースで十分ではないかと思うわけである。
AOURのような拡張定義を持つ入力方式も、最近考案された方式の中には少ないという気もしている。行段系の方式においては、ベースとなるアルファベット配置を元に無拡張の、すなわちローマ字入力同様の単文字対応の入力定義のみを備えているのが一般的であって、Dvorak JPやJLOD、ACT、gACT10、そしてAOURのような拡張定義型の方式は、もしかしたら今はその新規登場の時代ではないのかも知れない。学習コストを考えたら、AOURのような、定義数が多い方式は習得までに時間がかかると思われている面もあるだろうし、拡張定義は文字対応の定義の意義が薄れる部分があるので、言語の観点からすると影響があるのではないかと思われている面も否定できない。
テキストエディタを知った頃
テキストエディタというアプリケーションの存在を知ったのは、まだPCに移行する前のことだった。テキストを編集するのにワープロソフトよりも文字入力や文章書きにも適したアプリケーションとのことだったので、当然にそれがどんなものかという興味は持ったが、結局は実際に使ってみるまでどのようなものかわからなかった。
書式に関する情報を持たない、単純にテキストだけのファイルを扱って、そのファイルの内容をどのように編輯するか、表示させるかを統制するのがテキストエディタというアプリケーションだとわかって、つまりはテキストファイルという中身をどのように処理するかという違い、当時Vectorに収録されている様々なテキストエディタを試し、更にテキストエディタがどのようなものかという知識を深めた。
結局、一番有名な秀丸だとか、あとは市販ソフトとしてのWZが良くて、これらは今でも使っているくらいに、普通に使うアプリケーションになった。
文章はテキストエディタで
文章書きのアプリケーションと言えばワープロソフトということになるのが、その昔の主流で、おそらくこれは今もそんなに変わらないと思うのであるが、その頃はテキストエディタで書くべきという意見も多く、それなりに意識している人たちは挙ってテキストエディタを使うようになった。
自分もその一人である。ワープロ専用機から乗り換えた当初は一太郎やWordなどのワープロソフトを使い始めて、これはこれでずっと高度なことが出来るのでそれで満足ではあったが、ただ文章を書くということやその書く環境を徹底してカスタマイズできるという視点、またその起動や動作速度、結果テキストの汎用性においてはテキストファイル+テキストエディタは優秀で、結局これを使うことになった。
秀丸もWZも、この頃から使い続けているアプリケーションである。
いずれはワープロソフトの役割はテキストエディタに置き換わるのか、などとも思いつつ、文書作成に関してはエディタではなくワープロソフトとの棲み分けが必要だろうと思ったが、そのうちにクラウド的なもの、ブログやオンラインでのOfficeソフトが当たり前になってきて、ブラウザがそのアプリケーションになってきた。
おそらく今ではテキストエディタもワープロソフトもレガシーなアプリケーションということになる。
今、例えばブログをWordPressで書く人で、テキストエディタで原稿を書いてそれをWordPressのフォームに貼り付けて、というやり方をする人はかなり少ないのではないか。文章書きもレイアウトも、もうWordPressのインターフェイスで全て完全に出来るし、コピーして貼り付ける手間も要らないので、それが主流になるのは自然なことである。
OpenTTD 15b-2
OpenTTDはようやく15.0 beta-2が出た。正式版はまだ少し先か。
更新したらフォントが汎用的なものになってしまったので、CFGファイル内にMS UI Gothicを記述して解決。新機能の検証はできるかどうか。
詳しくは別の記事。
PC文章書きの環境
このような、PCにおいての文章書きは、以前はアプリケーションを使って書くのが当然で、今ではWebツールなどを使って書いてクラウドに保存というスタイルが主流なのであろうと思う。自分もそういう主流のスタイルを使うこともあるが、例えばこのブログの記事文などへ基本的に従来通りアプリケーションを使って書いている。
文章書きのアプリケーションと言って、だいたいはワープロかテキストエディタかということになる。もちろん自分もワープロソフトとして一太郎は使うが、主な文章書きとしてはやはりテキストエディタである。具体的にはWZ EDITORである。
テキストであることでの汎用性が高いという面もあるが、アプリケーションにおける環境、要は画面の配色だとか文字の大きさだとかの見た目部分などが一番書きやすいと思えるようにカスタマイズができるし、ワープロも動作が緩慢というわけではないがエディタの方が快適であるので、そのような理由からテキストエディタを使ってこのような文章を書いている。
希には印刷して文章を推敲したりもするが、その頻度は少ない。印刷する場合はワープロのほうが良い面は当然あるが、WZでも原稿確認程度の印刷だとか、それ以上に満足のいく印刷ができるようになっているので、結局WZがあれば文章書き作業については何の問題も無いということになっている。
キーボードはRealforceで、テンキーレス環境あるいは70%の環境に独立したテンキーを左側に配置して、それを入力環境としている。キーボードの配列はUS配列で、これは和文入力に不利と思われがちだが、全く遜色はなく、とにかくキー配置のバランスがJISよりも幾分良い分、ストレスが少なく入力ができている。
さらには、通常のローマ字入力は使わず、Dvorak配列ベースに定義した独自の入力方式AOURを使っているので、ローマ字入力より打鍵数が少なく、疲労も少ない方式で入力が出来ている。
結局、このような文章は同じようなことの繰り返しで書いているに他ならないのであるが、だいぶこの辺で書き溜まったようであるのと、WordPressを6.8に更新したので、その動作テストも兼ねることにして投稿しておくことにした。